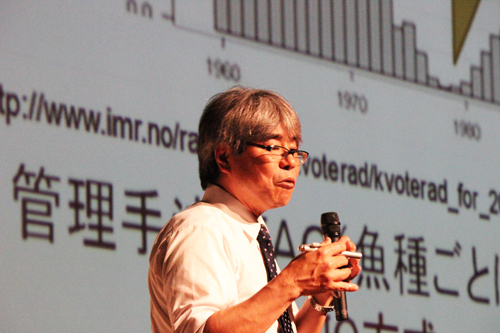年別アーカイブ: 2016年
京都スマートシティエキスポで「.kyoto」の意義をアピールしました
ICT(情報通信技術)による次世代の都市の在り方を探る「京都スマートシティエキスポ」が2016年6月1~3日,国立京都国際会館と京都府が運営する学術研究施設「けいはんなオープンイノベーションセンター」(KICK,木津川市・精華町)で開かれ,京都情報大学院大学(KCGI)サイバー京都研究所(CKL)が協賛し出展,木戸出正継CKL所長(KCGI教授)が講演してKCGIが管理運営事業者(レジストリ)を務める地理的名称トップレベルドメイン「.kyoto」の意義についてアピールしました。
木戸出所長はKICKで3日に催されたスマートシティセミナー「スマートコミュニティ形成へのKICK発イノベーション」で「実世界とサイバー社会の融合を目指して~ドット京都の普及拡大」と題して講演。「.kyoto」について「ドメインはコンテンツの発行元を示す極めて重要な意味を持っています。サイバー世界の中で,京都から一元的な情報発信をすることが大事。世界的に知名度の高い京都ブランドの品格を維持するためにもこの新しいドメインが存在する意義があります」と強調。KICK内に府から同センター拠点研究活用計画として第1号認定を受けて昨年6月開設したCKLが,インターネット上のサイバー世界と実世界を融合させる拠点であるとし「ドット京都は教育機関が管理運営し,産官学合同の公益事業として位置付けています。他のトップレベルドメインは乱発・乱売により残念ながらきちんと管理されていないケースが多いのですが,“.kyoto”はクリーンを追求しながら,京都全体の国際的な知名度・ブランド力のさらなる向上につなげ,社会・経済活動の活性化に導くことができるよう知恵を絞っていきたい」と話しました。一方,CKLの出展ブースには多くの方に来ていただきました。
「.kyoto」は2015年6月にサイバースペースに誕生,現在,一般登録を受け付けています。CKLは2015年5月26日,京都府との間で,「.kyoto」を使った京都ブランドの発信強化などを盛り込んだ連携・協力に関する包括協定を締結しています。
李弘燮 元KCGI教授が韓国・個人情報保護委員長(大臣級)に就任
京都情報大学院大学(KCGI)でかつて教授として教壇に立っていた李弘燮(Hong-sub Lee)氏がこのほど,韓国政府より大統領府直属個人情報保護委員会委員長(大臣級)に任命されました。任期は2016年5月30日から2019年5月までです。韓国も日本と同様,情報セキュリティの強化が急がれています。知識とご経験が豊富な李元教授の手腕に,韓国政府・国民の期待が集まります。
李弘燮 元教授は韓国・情報保護最高責任者協議会(CISO)会長に就任するため,KCGIから離れられました。同時に韓国大統領府直属個人情報保護委員会委員(コミッショナー),建国大学教授としても活躍。2013年6月1日に国立京都国際会館で開かれたKCGグループ創立50周年記念式典には来賓としてお越しになり,祝辞を述べていただきました。
李弘燮 元教授は韓国・漢陽大学校大学院修士課程修了(電子工学専攻)、大田大学校コンピュータ工学博士で,アジア/韓国PKIフォーラム議長,韓国情報保護振興院(KISA)院長,韓国保護学会会長などを歴任されています。KCGIでは「情報セキュリティ/PKI」を担当,▽サイバー犯罪対応のための政策 ▽ハッキング,ウイルスなどに対する技術的対応 ▽安全な情報システム運営に必要なISO国際情報セキュリティ管理基準などに対する分析 ▽インターネット上での身分確認と取引情報の無欠性維持のためのPKI基準認証技術― などについて学生に教授していました。
※ PKI(Public Key Infrastructure,公開鍵暗号方式を利用したセキュリティインフラ)

KCGとKCGIが京都府警と人材育成に関する協定を結びました

京都コンピュータ学院(KCG)と京都情報大学院大学(KCGI)が「サイバー空間の脅威への対処を担う優秀な人材の育成に関する協定」を京都府警と結びました。調印式は5月31日,KCG京都駅前校で行われ,KCGグループからは,長谷川亘KCGI理事長と長谷川晶KCG理事長,京都府警からは,石丸洋 京都市警察部長が出席し,協定書にサインしました。府警では,通信技術を悪用したサイバー犯罪に的確に対処するために,サイバー特別捜査官を育成する制度を2年前に設け,この春からは2期生の研修が始まりましたが,この協定に基づいて,KCG・KCGIのIT(ICT)に関する基礎的なクラスでの学習が,その研修カリキュラムに組まれることになります。府警では,研修生がIT(ICT)の基礎知識と技能を早い時期から学ぶことで,サイバー空間の脅威に対処する人材の育成が効果的に行われると話しています。
また,相互交流として,KCG・KCGIの学生が警察業務の見学・体験をすることや,第一線の現場で働く警察官が講師として,KCG・KCGIで授業を持つことも計画されていて,今後,KCGグループと京都府警との人的交流がさらに活発になることが期待されます。今回の調印式には,NHK・KBS・京都新聞が取材に訪れ,サイバー空間の安全の問題に対する一般の関心の高さもうかがわせていました。
5月28日アート・デザイン系オープンキャンパスを開催しました
5月21日アート・デザイン系オープンキャンパスを開催しました
『Unreal Engine4 (UE4)』勉強会がKCGで開催されました

『Unreal Engine4 (UE4)』を使用したゲーム開発を専門に行う株式会社ヒストリア主催のUE4勉強会イベント「出張ヒストリア!UE4京都勉強会」が5月15日(日),京都コンピュータ学院(KCG)京都駅前校の大ホールにて開催されました。UE4アカデミックパートナーとして認定されているKCGのデジタルゲーム学系の教員と学生たちは,イベントスタッフとして当日の運営にも参加させていただきました。
前日に大阪で開催されたUE4イベント「UNREAL FEST OSAKA 2016」は,中級者〜上級者向けの講演が中心でしたが,本学院で開催された「出張ヒストリア!UE4京都勉強会」では,これからゲーム業界を目指す学生にもわかりやすいように,初心者〜中級者向けの講演が中心でした。 講演では,入社したての新人プランナーとアーティストがわずか数カ月で制作に挑んだゲームアプリ開発についての事例や,ゲーム業界で注目されているVR(バーチャルリアリティー)コンテンツ開発や技術共有についてご紹介いただきました。充実した内容で,参加者と講演者による意見交換が盛んに行われていました。

また,今回の勉強会ではVR用ヘッドマウントディスプレイ「HTC Vive」の体験会も実施され,KCGの学生スタッフが,参加者への操作説明やサポートも担当いたしました。スタッフを務めた学生にとっては「HTC Vive」が体験できただけでなく,参加者への操作サポートを通じてプレイヤーの反応を見ながら,さまざまな感想を聞くことができ,今後,ゲーム業界を目指す上で大切なことを学ぶ機会となりました。このような貴重な機会をいただき,ありがとうございました。


5月8日にオープンキャンパスを開催しました
京都コンピュータ学院創立53周年記念式典を挙行

京都コンピュータ学院(KCG)創立53周年の記念式典を4月29日,KCG京都駅前校6階の大ホールで挙行しました。
記念式典では京都情報大学院大学(KCGI)の中村行宏教授が,「京都コンピュータ学院で学ぶこと」と題して,KCGの学生に向けて記念講演をしました。
中村教授は,企業や大学での自らの研究キャリアをふり返りつつ,これからの社会でITやICTが果たす役割の重要性を強調し,第四次産業革命とも呼ばれ,IoT(Internet of Things)も進められる現代では,次の10年間に500億から1兆個ものデバイスがインターネットに接続されると予測され,このネットワークから得られるビッグデータを蓄積・分析して,新たな価値と知恵の創造につなげることが大切になってくると話しました。
その上で,この情報と物理的な世界が一体化しつつある社会では,IT・ICTこそが社会システムの基盤を構築する技術であることから,この分野の教育で先陣を切ってきたKCGに在籍している利点を最大限に活かして,全力で勉強してくださいと,会場の学生を激励しました。

古野電気株式会社による特別講演会が開かれました
「海洋ITの今と未来を担う 〜古野電気からのメッセージ〜」と題した,古野電気株式会社による特別講演が,4月22日,京都コンピュータ学院(KCG)駅前校の6階大ホールで開かれ,大勢のKCGの生徒たちが聴講しました。
古野電気は船舶や産業用の電子機器製造販売会社で,1948年に世界で初めて魚群探知機の実用化に成功しました。本社は兵庫県西宮市にあります。
講演では,最初に古野電気技術研究所の西森靖氏が,「古野電気の研究開発 魚探誕生から現在そして未来」と題して,古野電気が魚群探知機の実用化に成功した経緯を紹介しました。この中で,創業者の古野清孝氏が,魚の体は超音波には反応しないという当時の通念にも関わらず,魚の浮袋は超音波を反射するはずという信念を持って開発にあたったことや,船舶の航行時に発生する泡が探知の障害になることから,その発生がもっとも少ない船底の中央に穴を開けてソナーを設置するという発想が,実用化の大きなはずみになったことなど,いくつもの興味深いエピソードが紹介されました。
西森氏はまた,漁業資源保護の観点から,日本でも船舶毎に漁獲量を割り当てるIQ制度導入の動きがあることを紹介し,その場合,特定の魚種や魚体長の魚を識別できる魚探への需要が増えることから,より高精度の魚探の開発に積極的に取り組んでいると話しました。
続いて,同技術研究所の今坂尚志氏が,古野電気における開発業務の仕事内容について,ハード・ソフト両面での設計から始まって,製品の試作,品質検査のための海上実験やフィールドテストへと進んでいく流れを,実例もまじえながら紹介しました。
また,古野電気が総合船舶用電子機器メーカーとしては,世界シェアのトップを占めている一方で,プレジャーボート向けの市場ではあまり強くないことを取り上げて,不得意分野で業績を伸ばすには,社外にパートナーやアイディアを積極的に求める「オープンイノベーション」が重要であることも説明しました。
最後に今坂氏は,古野電気の研究・開発に向いている人材の特徴を,KCGのイニシャルにひっかけて,次のように表現しました。K:考えるのが好き,C:コミュニケーションが好き,G:我慢強い。
KCGグループでは,2015年に当グループと産学連携協定を結んだ古野電気の協力を仰ぎながら,海洋ITの教育に力を入れていきます。本年度から,KCGの応用情報学科に全日制3年課程の海洋ITコース,京都情報大学院大学(KCGI)の次世代産業コースに海洋ITプログラムを新設して,この分野をリードする人材の育成に努めます。