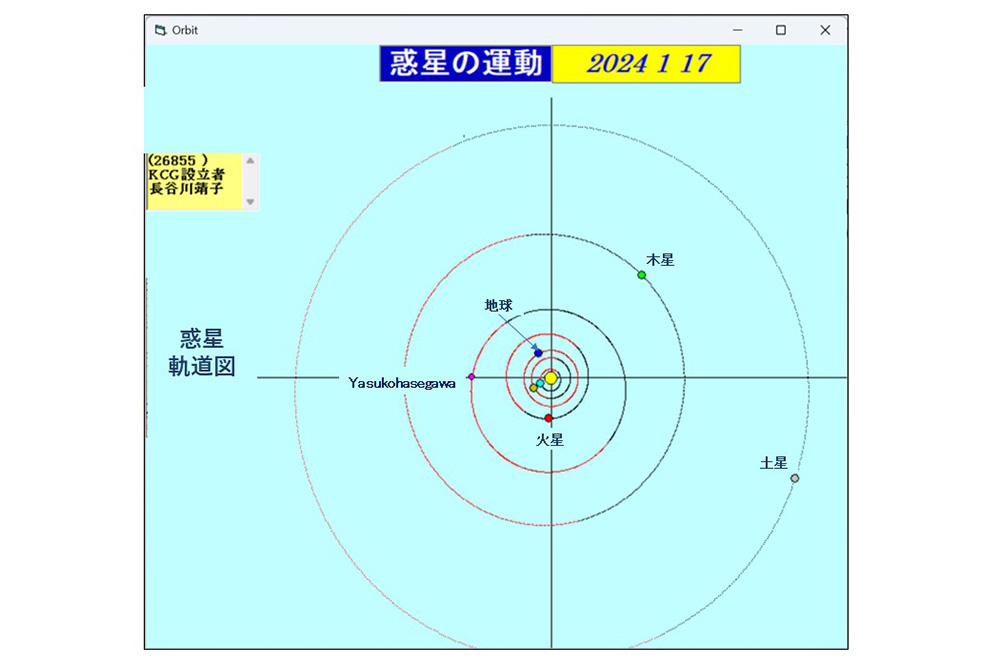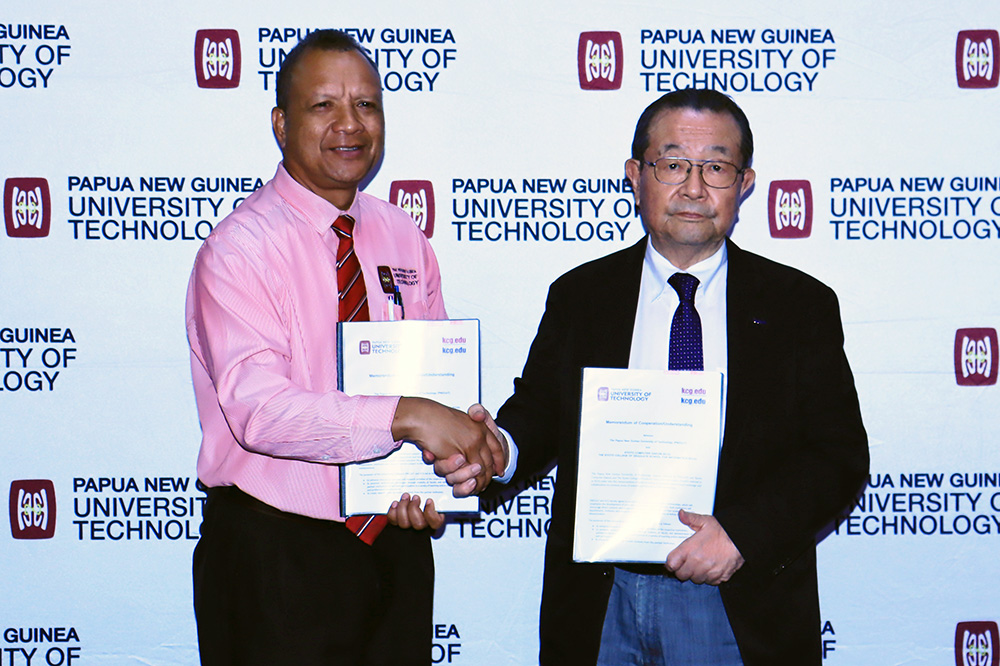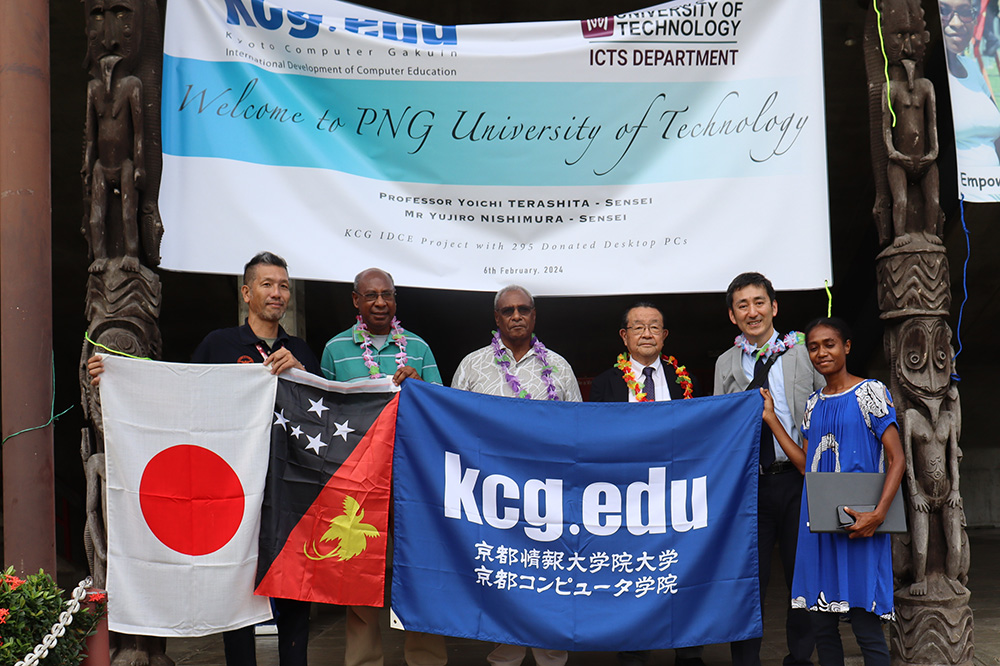京都コンピュータ学院(KCG)の学生が1年間の学習・研究成果の集大成として開発,制作した作品を発表する「KCG AWARDS 2024-学生作品発表会-」は2024年2月25日(日),KCG京都駅前校6階大ホールで開かれ,6グループ・個人がプレゼンテーション形式で成果を披露した結果,最優秀賞にはエンジニアリング学系の髙橋さん(情報工学科),岩堀さん,田邊さん(コンピュータ工学科自動車制御コース),生駒さん(同コンピュータ工学コース)による自転車に装備するデバイス「Cycle Safety Computer」が輝きました。審査員はKCGの卒業生を含めたIT業界関係者6名が担当,「例年にも増してレベルが高く,その中で楽しみながらプロジェクトに取り組んでいる様子が垣間見られた。特にプレゼンテーションがいずれも素晴らしかった」との評価をいただき,KCGの学生たちに向け「最近はモノづくりに加え,コトづくりと言われる。取り組んでいるものが完成すると,どのような結果が生まれるのか,そして社会的課題を解決できるのか。そのような視点を持って,これからも頑張ってほしい」とのエールを送っていただきました。
2月8,9日に,「プロジェクト演習発表会」を開催し,その中から優秀賞に選ばれた6作品をこの日,あらためて発表。ゲストとして,グループ校の京都情報大学院大学(KCGI)の廣瀬さんがマスタープロジェクトの優秀作品「ChatGPTとLinked Open Dataを用いた 問題作成支援手法の提案」を発表しました。司会進行は情報処理科 IT声優コースの垣尾さんと藤田さんが担当。当日の模様は,オンラインによりライブ配信されました。
審査員は,富士通Japan株式会社 ソリューショントランスフォーメーション本部 シニアマネージャーの桝野弥千雄さん,BIPROGY株式会社 総合技術研究所 主席研究員の三浦仁さん,AI/ストラテジースペシャリスト シリアルアントレプレナーの清水亮さんと,KCG卒業生でいずれも学生当時「KCG AWARDS」に出場したアマゾンウェブサービスジャパン合同会社の前田駿介さん(情報科学科卒業,2016最優秀賞),株式会社タイミーの岐部龍太さん(ネットワーク学科卒業,2008最優秀賞),株式会社ディー・エヌ・エーの松田唯史さん(情報科学科卒業,2008出場)の計6名にお願いしました。審査員のみなさんからは,それぞれの作品についての細かい講評やアドバイスをしていただき,学生たちには今後制作活動を続けるうえで,大きな励みになりました。
詳しい内容は,「KCG AWARDS 2024-学生作品発表会-」ページに掲載しています。どうぞご覧ください。
KCG AWARDS 2024-学生作品発表会-
https://www.kcg.ac.jp/event/awards2024.html